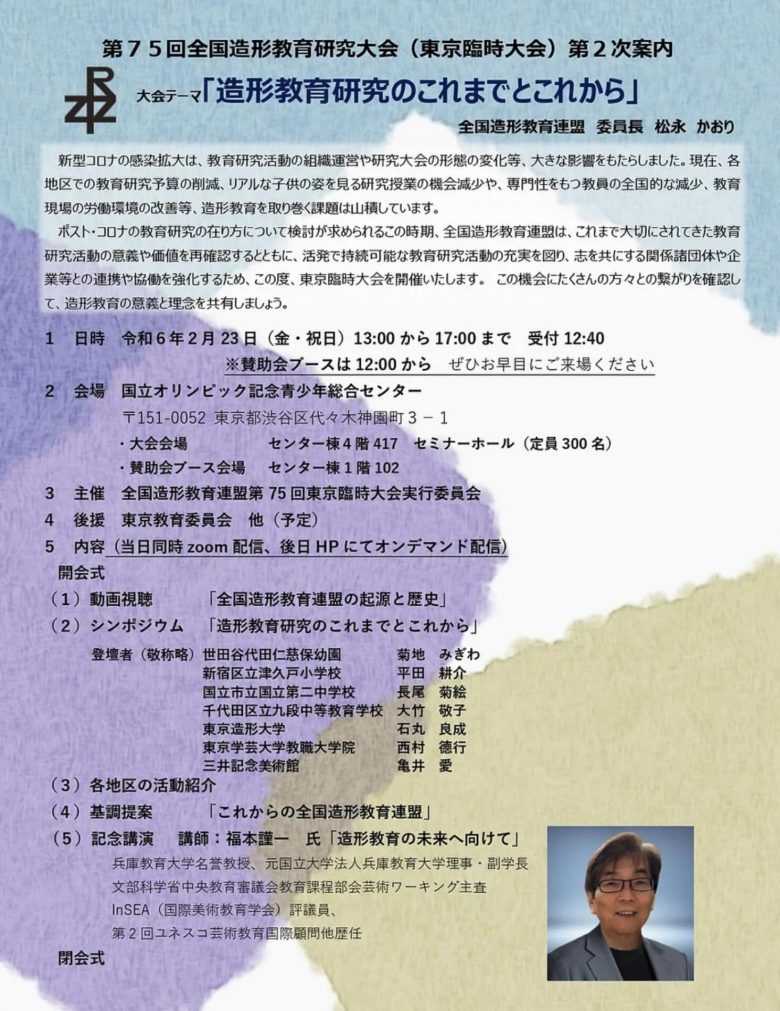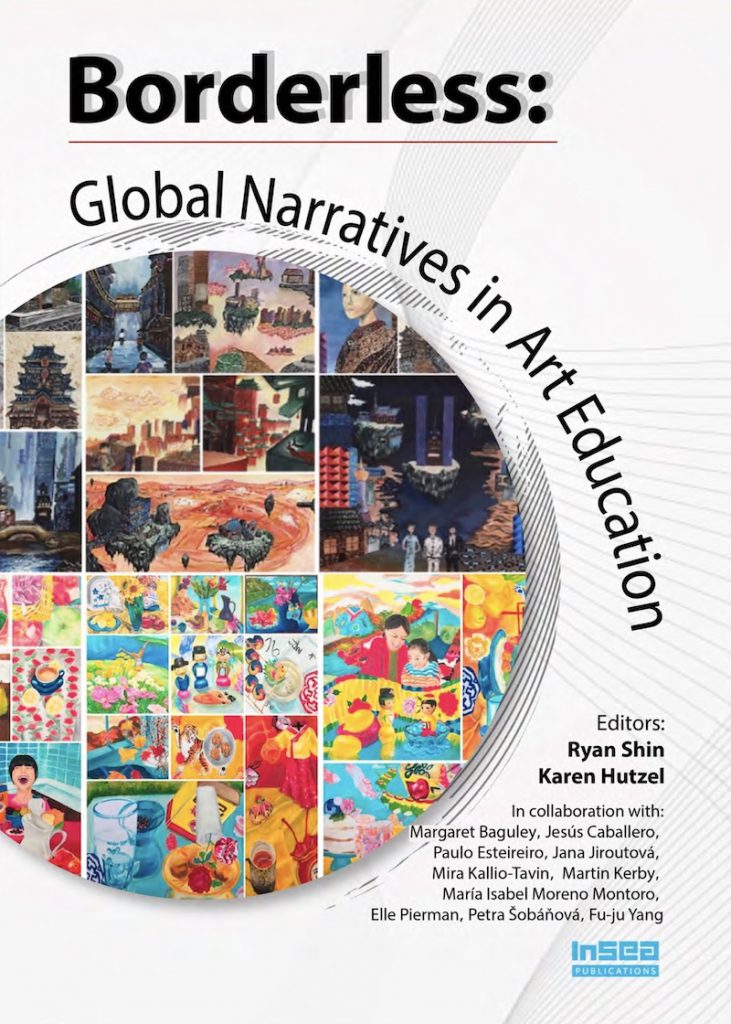「造形遊び」
2012年5月7日
美術教育の専門誌「美育文化」2012 vol.62 No.3 5月号の特集は「造形遊び」
中学校の学習内容にはないので中学校の教師は「造形遊び」のことを十分理解せず、授業で「遊び」?となったりすることもあります。それが、そのまま小学校の一部でもそのように思われている面もあります。そのような実態から「造形遊びの逆襲」という特集が組まれました。
「造形遊び」について理解するには 非常にわかりやすいものです。
この特集にあたり、「美育文化」誌では、特集に先立って以下のような文章を掲載しています。WEBサイトから以下に転載させていただきました。
今日の「造形遊び」が「造形的な遊び」といういささか遠慮がちな名称により学習指導要領に導入されたのは、昭和52(1977)年、今から35年前のことだ。
造形遊びの登場は、それまでの「絵画」「彫塑」「デザイン」「工作」「鑑賞」というあくまで大人の美術観によっていた教科の枠組みに、「子どもの自然発生的な造形活動」という視点を盛り込んだ。これは目的に基づいた造形表現という定式化された活動を、素材や身体性に対する興味関心や遊びの中から、たまたま始まってしまうような表現にまで拡張し、造形表現をより根源的なものに拡げたと言える。
その後、造形遊びは平成元(1989年)に中学年に、平成10(1999)年には高学年にまで順次拡大され、教科を貫く柱として位置づけられた。造形遊びの出自については幾つかの説がある。一つは、デザイン教育系の教育者らがバウハウスの教育メソッドを参照したとするものであり、ここには造形遊びの表現性と教育的意義に注目する視線があった。他方、関西の具体美術協会の影響下にあった若手の教員らが60年代に始めた「DOの会」などの活動にその源流をみる見方もあり、ここでは主として活動の身体性が主眼となっていた。また、東京都図画工作研究会がドイツのワークショップに触発された実験授業を行ったことがきっかけになったという見解もある。ここでは「素材感」ということが中心課題であった。
だが、これらのどれが造形遊びのルーツであるかという議論は本質的なことではない。重要なことは、70年代の記号論、脱構築理論、精神分析、エスノグラフィー(民族学)などの「学」そのものの解体を目指すような多元文化論への関心が、「子どもの再発見」という理念を自覚させ、それが様々なコンテンポラリー・アートの方法と偶然にあるいは必然的に交響したということである。
けれども、当初の導入から30年余を経た今日、造形遊びがこの教科の中核的な活動としてどっしりと位置づけられ、図工教育の一般的な授業形態として定着しているとは言い難い。むしろ、子ども中心主義の理想から後退している状況がある。
なぜそうなってしまったのか、その背景には社会の大状況と教科の内部事情があった。
教科の内部事情というのは、未だに従来の美術文化のジャンル意識を残存させている体質が根本にあることだ。このメンタリティからの現代美術への心理的反発が造形遊びに及んでいるきらいは大いにある。
個別の問題としては、造形遊びがあたかも大量の造形素材を使用してイベント的な授業を展開する活動でもあるかのように誤解されたことや造形遊びが評価しにくいと思われたことなども定着を阻害した要因だろう。
けれども、これらよりも大きなことは、直ちに結果を求める成果主義の風潮が、子ども中心の造形活動という理念を許容する度量を持ちえなかったことではないだろうか。
今次の教育の中心課題とされている言語活動の充実や鑑賞教育の充実が、その深層に本来の意図を問われないままに子どものプリミティヴィズムとすれ違っているとすれば不幸なことだろう。
現行の指導要領より導入された〔共通事項〕は、「表現」と「鑑賞」に架橋を渡すものであり、また小学校図画工作科と中学校美術科をなめらかに連携させる意図をもっている。しかし、これを安直に指導内容として理解することは、この教科を「色と形とイメージの学習」というお堅い内容に塗り替えてしまいかねない。
子どもたちをめぐる視覚世界は確かに拡張された。それゆえ、そのためのリテラシーの獲得などは重要な教育課題だ。けれども一方、素材に対する飢餓感、身体性や総合的な感覚についての関心・期待、あるいは、表現をすることに伴う場や時間に対する意識など「色と形とイメージの学習」に付随する重要なファクターはいくらもある。
造形遊びに託された「子ども主体の授業」や「遊びの教育的意味」はまったく色褪せてはいない。むしろそれこそが希望であることを私たちは改めて自覚するべきではないだろうか。
レポーター:山崎 正明